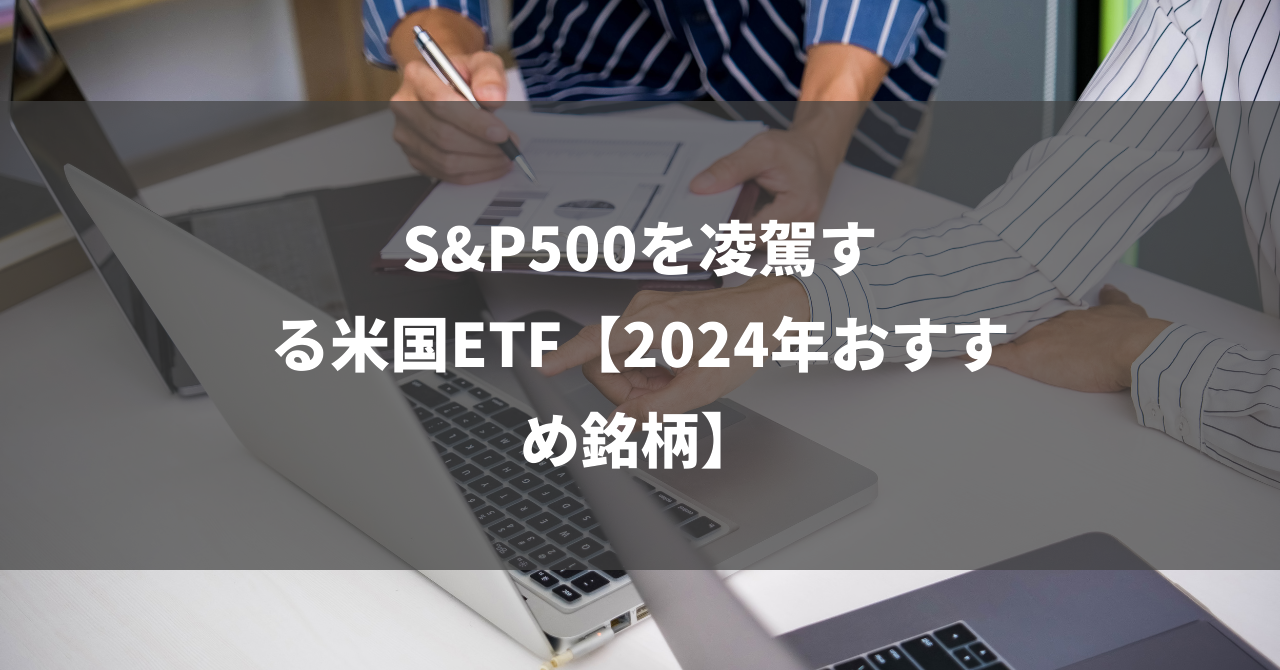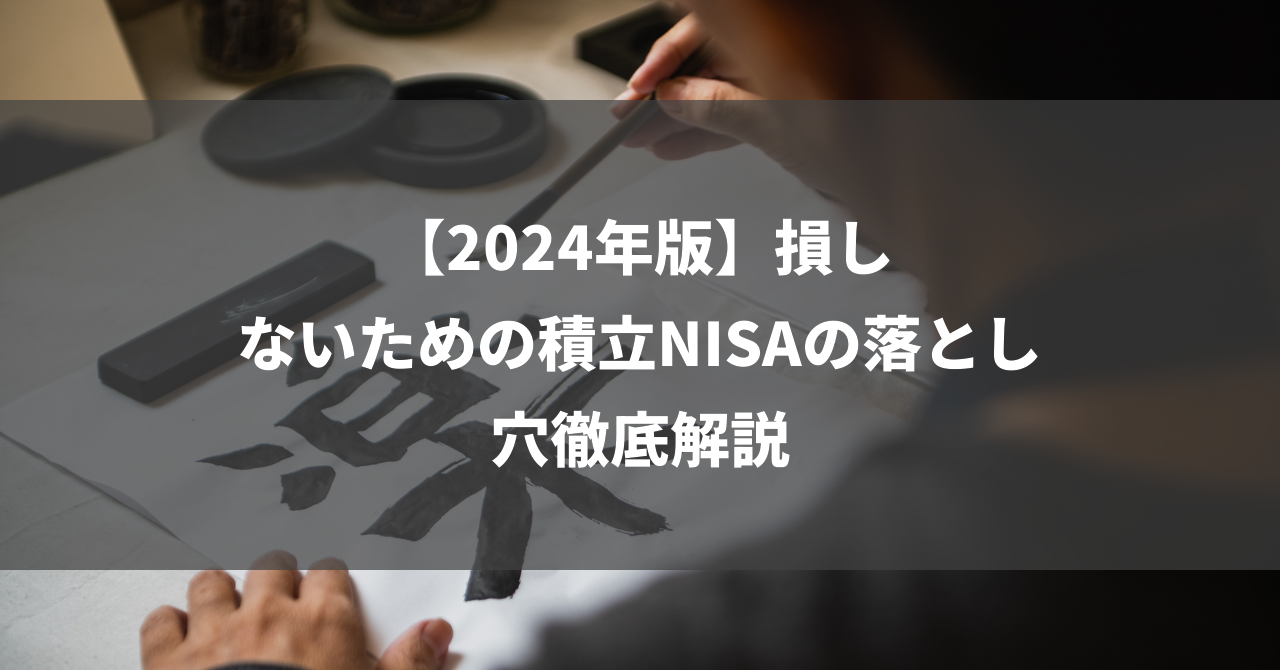貧乏になる格差社会を抜け出すために
貧乏になる格差社会を抜け出すための方法について考えていきたいと思います。人によっては元からお金持ちに生まれた方もいらっしゃいますが、多くのサラリーマンは日々働いて生計を立てています。そんな中で登場したのが老後2000万円問題。お金持ちの人には関係ないかもしれませんが、多くのサラリーマンにとって2000万円を貯めるのは非常に難しい課題です。さらに現在では格差社会がどんどん広がっています。この記事では、格差社会をどう捉え、どう対処すべきかについて、私の実体験を交えて話していきます。
目次インフレとデフレの重要性
まず、老後資金を考える上で重要になるのがインフレとデフレです。インフレは貨幣価値が落ちて物価が上昇する現象を指し、デフレはその逆で貨幣価値が上昇し物価が下がる現象を指します。例えば、100円で買えたリンゴが150円に値上がりするのがインフレ、逆に100円が50円に値下がりするのがデフレです。インフレが進むと現在の2000万円の価値が将来低くなり、デフレが進むと逆に価値が上がることになります。
日本の消費者物価指数を見てみると、1970年から高度経済成長期にかけて物価が急上昇しましたが、1990年代後半から横ばいが続いています。また、1990年代後半から2000年にかけては若干のデフレ傾向が見られました。そのため、多くの消費者はインフレよりもデフレの感覚を持っているかもしれません。しかし、経済的にはわずかなインフレが続くことが望ましいとされており、これは消費を喚起し経済の循環を促すためです。
隠れインフレとその影響
隠れインフレという現象も見逃せません。例えば、カントリーマアムやエンゼルパイなどの商品が小さくなったり、ポテトチップスの内容量が減少するなど、実質的な値上げが進行しています。これにより、公式の消費者物価指数以上にインフレが進行している可能性があります。つまり、貯金だけでは将来的に貧乏になるリスクがあるということです。
収入の減少とその影響
次に、お金をもらう際の話に移ります。私の過去の動画でも触れましたが、手取り収入は年々減少しています。例えば、年収700万円の手取りが2002年には587万円だったのに対し、現在では530万円程度に減少しています。これは税額控除の減少や社会保険料の拡大、厚生年金の負担増加などが原因です。収入の減少と物価の上昇が同時に進行しているため、実質的な生活費の負担が増しています。
アベノミクスと格差の拡大
さらに、経済全体ではアベノミクスによる好景気が続いていました。特に、株式市場は大幅に上昇し、日経平均は2011年から現在まで約3倍に増えています。ただし、これは一部の投資家にとって有利な状況であり、平凡なサラリーマンとの格差を広げる要因となっています。また、配当金の税率が20.315%と低めに設定されている一方で、給与所得には高い所得税や住民税、社会保険料が課せられています。
配当金と税制の違い
配当金に対する税率は20.315%であるのに対し、給与所得には所得税、住民税、社会保険料がかかります。所得税は300万円から700万円の人で約20%、住民税が約10%、さらに社会保険料も加わります。結果として、配当金よりも多くの税金や社会保険料を支払わなければならないのが現状です。これが、資産を持つ人と持たない人の格差を広げる一因となっています。
社会保険料の負担
社会保険料もまた大きな負担です。年収300万円の人は年収に対して15.8%を社会保険料として支払い、一方で年収1000万円の人は12.9%を支払います。年収が高ければ高いほど、社会保険料の負担割合が減る仕組みとなっています。このように、社会保険料も格差を広げる一因となっています。
脱出するための方法
このような厳しい現実に対して不平不満を言うだけでは生活は改善しません。そこで、現実と向き合いながらも抜け道を探すことが重要です。以下にいくつかの方法を紹介します。
1. 投資を始める
- 配当金に対する税率は20.315%であるため、有利な税制が受けられます。また、積み立てNISAやiDeCoといった税制優遇のある制度を利用すれば、さらにメリットが大きくなります。
2. 副業を始める
- ネットで完結できる副業や多種多様な副業があり、これらを活用することで収入を増やすことが可能です。青色申告を利用すれば税額控除も受けられます。
3. 支出の見直し
- 例えば、通信費の見直しや節約術を活用することで、支出を抑えることができます。
関連する質問と回答
インフレとデフレの違いは何ですか?
インフレは貨幣価値が下がり、物価が上昇する現象です。一方、デフレは貨幣価値が上がり、物価が下がる現象を指します。インフレが進むと現金の価値が下がるため、貯金だけでは資産が目減りするリスクがあります。
隠れインフレとは何ですか?
隠れインフレとは、商品のサイズが小さくなったり、内容量が減少するなどして実質的な値上げが行われる現象を指します。公式の物価指数には反映されにくいですが、実際の生活コストが上昇するため注意が必要です。
社会保険料の負担はどのように変わりますか?
社会保険料は年収に応じて変わります。年収が高いほど負担割合が減る仕組みとなっており、年収300万円の人は15.8%、年収1000万円の人は12.9%を支払います。
投資を始めるメリットは何ですか?
投資を始めることで、配当金に対する低い税率を享受できるだけでなく、積み立てNISAやiDeCoといった税制優遇制度を利用することで、資産形成を効率的に行うことができます。
副業を始める方法は何ですか?
ネットで完結できる副業や多種多様な副業があります。例えば、ブログ運営やYouTubeチャンネル、せどりなどが代表的です。これらを活用することで収入を増やし、青色申告を利用すれば税額控除も受けられます。